目次
簡易金型とは?量産金型との違いを再確認
「そもそも簡易金型とは何か?」その基本から、量産で使う量産金型との違いまでを改めて整理しましょう。両者の特性を正しく理解することが、最適な金型選びの第一歩です。
そもそも簡易金型とは?試作・小ロットに特化した金型
簡易金型とは、その名の通り、試作品の製作や小ロット生産に特化して作られる金型のことです。本格的な量産に入る前に、製品の形状、機能、組付け性などを検証することを主な目的としています。
製品開発の現場では、設計データだけでは分からない問題点を確認するため、実物に近い試作品が不可欠です。簡易金型は、こうした開発初期段階のニーズに応えるため、製作コストや納期を大幅に短縮することを目指して設計されています。そのため、金型の材質に比較的安価で加工しやすいアルミ合金などを用いることが多く、設計も量産用の量産金型に比べて簡略化されているのが特徴です。数十個から数千個程度の小ロット生産に対応できるため、限定製品やテストマーケティング用の製品製造にも活用されています。
目的と用途から見る量産金型との根本的な違い
簡易金型と量産金型の最も根本的な違いは、その「目的」にあります。簡易金型の目的が「試作品による検証・確認」および「小ロット生産」であるのに対し、量産金型の目的は「数十万ショット以上の安定した大量生産」です。この目的の違いが、金型の仕様や価格、納期に大きく影響を与えます。
例えば、「検証・確認」が目的の場合、簡易金型は開発スピードを重視し、設計が正しいか、市場の反応はどうかといった評価を行うためのツールとして活用されます。そのため、金型の耐久性はある程度割り切って設計されるのが一般的です。
一方で、「小ロット生産」が目的の場合、簡易金型は生産設備としての役割を担います。年間生産数が数百〜数千個程度の製品や、市場投入前のテストマーケティングなど、量産金型を作るほどの投資はできないが、一定数の製品が必要というニーズに対応可能です。
対照的に、量産金型は長期間にわたって同じ品質の製品を安定供給することが最も重要な目的となります。そのため、焼入れ処理を施した高硬度の鋼材を使用し、冷却機構やガス抜きといった細部に至るまで、量産効率を最大化するための複雑な設計が施されるのが一般的です。
【一覧表】メリット・デメリットで比較する簡易金型と量産金型
簡易金型と量産金型のどちらを選択すべきか。それはプロジェクトの目的や予算、必要な生産数によって決まります。両者の特性を一覧表で比較し、判断材料としてご活用ください。
| 比較項目 | 簡易金型 | 量産金型 |
| 目的 | 試作・小ロット | 大量生産 |
| ショット数 | 数十~数千 | 数万~数十万 |
| 材質 | アルミ・鋼材 | 鋼材 |
| 納期 | 2週間~ | 6週間~ |
| 費用 | 低い初期投資 | 高い初期投資 |
このように、両者には明確な長所と短所が存在します。簡易金型は、まさに開発段階における「時は金なり」を体現するソリューションと言えるでしょう。
【比較】簡易金型の費用相場と納期はどれくらい?

ここからは、開発担当者の方が最も知りたい「具体的な費用と納期」について解説します。プロジェクトの予算とスケジュールを組む上での、リアルな数字感をご確認ください。
簡易金型の費用感 - 量産金型の50%〜70%程度も
簡易金型の製作費用は、一般的に数十万円からというのが一つの目安です。数百万円から時には一千万円を超えることもある量産金型と比較すると、そのコストメリットは明らかです。製品のサイズや形状、構造の複雑さによって費用は変動しますが、量産金型の50%〜70%程度の費用に抑えられるケースも少なくありません。
このコスト削減を可能にしている最大の理由は、金型の材質と構造の簡略化にあります。簡易金型では、切削加工がしやすいアルミ合金を主に使用するため、材料費そのものを安くできる上に、加工時間を短縮することで人件費も削減できます。また、量産を前提としないため、金型内の複雑な冷却機構などを省略し、シンプルな構造にすることで、設計・製作にかかるトータルコストを削減しているのです。この初期投資の大幅な削減は、特に予算が限られる開発プロジェクトにおいて大きな強みとなります。
圧倒的なスピード感!簡易金型の納期目安
簡易金型のもう一つの大きなメリットが、その圧倒的な納期の速さです。通常、量産金型の製作には早くても1ヶ月半、複雑なものでは数ヶ月を要します。これに対して簡易金型は、最短で2週間から4週間程度での製作も可能です。このスピード感が、開発リードタイムを劇的に短縮し、市場投入のタイミングを早める強力な武器となります。
この短納期を実現しているのも、やはり加工しやすいアルミ合金の使用と、シンプルな金型構造によるものが大きいです。切削加工の時間が短いことに加え、金型の組み立てや調整にかかる工数も少なく済むため、発注からトライショット(試し打ち)までの期間を大幅に短縮できるのです。競合よりも早く製品評価を完了させ、次の開発フェーズに進むことができるため、ビジネスチャンスを逃さないためにも、簡易金型のスピードは非常に価値があると言えるでしょう。
【価格の決まり方】簡易金型の費用相場と納期を左右する3つの要因
「A社とB社で見積もり金額が違うのはなぜ?」その疑問を解消するため、価格を決定づける代表的な3つの要因を掘り下げます。このポイントを押さえれば、見積もりの内訳を正しく理解できるようになります。
要因①:金型材質(アルミ・鋼材)の違い
金型に使用する材質は、費用と納期に最も直接的な影響を与える要素です。簡易金型で主に使用されるのは「アルミ合金」と「鋼材(NAK材など)」の2種類で、それぞれに異なる特徴があります。
アルミ合金は、鋼材に比べて材料単価が安く、非常に柔らかく加工しやすいという特性を持ちます。そのため、金型を削る時間を大幅に短縮でき、結果として低コスト・短納期を実現する大きな要因となっています。とにかく早く、安く試作品を作りたい場合には最適な選択肢です。ただし、耐久性は鋼材に劣るため、多くのショット数には向きません。
一方、鋼材はアルミ合金よりも硬く、耐久性に優れています。そのため、数千ショットといった、簡易金型としては比較的多めの生産数に対応可能です。また、製品表面に模様をつけるシボ加工など、より量産品に近い外観品質を求める場合にも鋼材が選ばれます。しかし、硬い分だけ加工に時間がかかり、材料単価も高くなるため、費用と納期はアルミ合金の金型よりも増加する傾向にあります。
要因②:製品の形状と複雑さ
作りたい製品の形状がどれだけ複雑かという点も、価格を大きく左右します。単純な箱のような形状であれば金型の構造もシンプルですが、側面に穴や凹凸がある「アンダーカット形状」が含まれる場合、金型に「スライド」と呼ばれる機構を追加する必要が出てきます。
このスライド機構は、金型を開閉する際に横方向に動く部品のことで、これがあるだけで金型の構造は一気に複雑化します。部品点数が増え、設計や組み立てにも手間がかかるため、その分だけ費用が上乗せされるのです。同様に、製品に求められる寸法精度が厳しい場合や、薄肉で細かいリブ(補強)が多い形状なども、金型の加工難易度が上がり、価格上昇の要因となります。製品のサイズが大きくなれば、当然ながら使用する材料も増えるため、それに比例して費用も高くなっていきます。
> スライドとは?
要因③:求めるショット数(寿命)
その簡易金型で、最終的に何個の製品を成形したいのか、という「ショット数」の要求も重要なポイントです。目的が「デザインや嵌合(かんごう)を確認するための数個の試作品」であれば、耐久性をあまり考慮しない最も安価な仕様の金型で十分でしょう。
しかし、「小規模な初期ロットとして1,000個生産したい」といった要望がある場合、それに耐えうるだけの耐久性を持った金型を設計する必要があります。具体的には、摩耗しやすい部分に硬い鋼材を部分的に使用する「入れ子」構造にしたり、より耐久性の高い鋼材を金型全体に使用したりといった対策が取られます。当然、こうした耐久性を高めるための工夫は、金型の費用に反映されます。
また、金型製作ではロット数だけではなく生涯生産数(年間生産数×生産年数)も重視して金型仕様を決定します。たとえ、「年一回の生産で500個」といっても「10年生産」であれば、生涯生産数は5,000個になります。生産ロットが少なくても生涯生産数が多い場合や、初回ロットから徐々に生産数を増やす場合などは、安易に安いアルミ型などを選択すると途中で金型更新の必要などが発生するリスクがあります。
これら「材質」「形状」「ショット数」という3つの要因が複雑に絡み合い、さらに各メーカーの設備や得意とする技術分野の違いが見積もりに反映されることで、価格差が生まれるのです。
【得意とする技術分野の違い】
同じプラスチック成形でも金型メーカーや成形メーカーごとに得意不得意がございます。
・業界:自動車や家電、住宅設備など業界ごとに標準品質などが異なります。高い品質には、コストも必要なため、価格差が生じる可能性があります。
・材料:購入している材料量によってもコストが変わります。普段使用していない材料を少量購入すると高くなる場合が多いため、場合によっては材料支給(依頼者側が成形メーカーに材料を支給)を検討しましょう。
このような価格のばらつきによる混乱を避け、適正な見積もりを引き出すためには、依頼者側が情報を明確に伝えることが何よりも重要です。見積もりを依頼する際は、少なくとも「①成形材料の情報」「②生産数量」「③3D CADデータ」の3点を必ず準備しましょう。これらを複数のメーカーに同じ条件で提示し、見積もりの内訳を比較検討することで、価格の妥当性を判断しやすくなり、プロジェクトに最適なパートナーを見つけることができるはずです。
|
成形材料の情報 |
成形材料は金型仕様に大きく影響します。数十個程度なら大丈夫ですが、100個を超えるのであれば注意が必要です。 |
|
生産数量 |
生産数は下記2つの情報に分けて情報提供しましょう。 ・年間生産数 ・生産年数(≒生涯生産数) 年間生産数によって金型の取り数を変更します。生産年数(≒生涯生産数)によって、アルミ型やカセット型が適しているのか判断できます。 |
|
3Dデータ |
近年のモノづくりでは3Dデータは必須です。 外注でデータ作成する場合は数十万円~数百万円かかり、金型以外の初期費用がかかるので、注意が必要です。 ※強度設計込みなどのケースでは解析などを行いながらデータを作成するため、数百万円のコストがかかるケースがあります |
海外企業の動向から学ぶ、日本市場で本当に頼れるメーカーの選び方
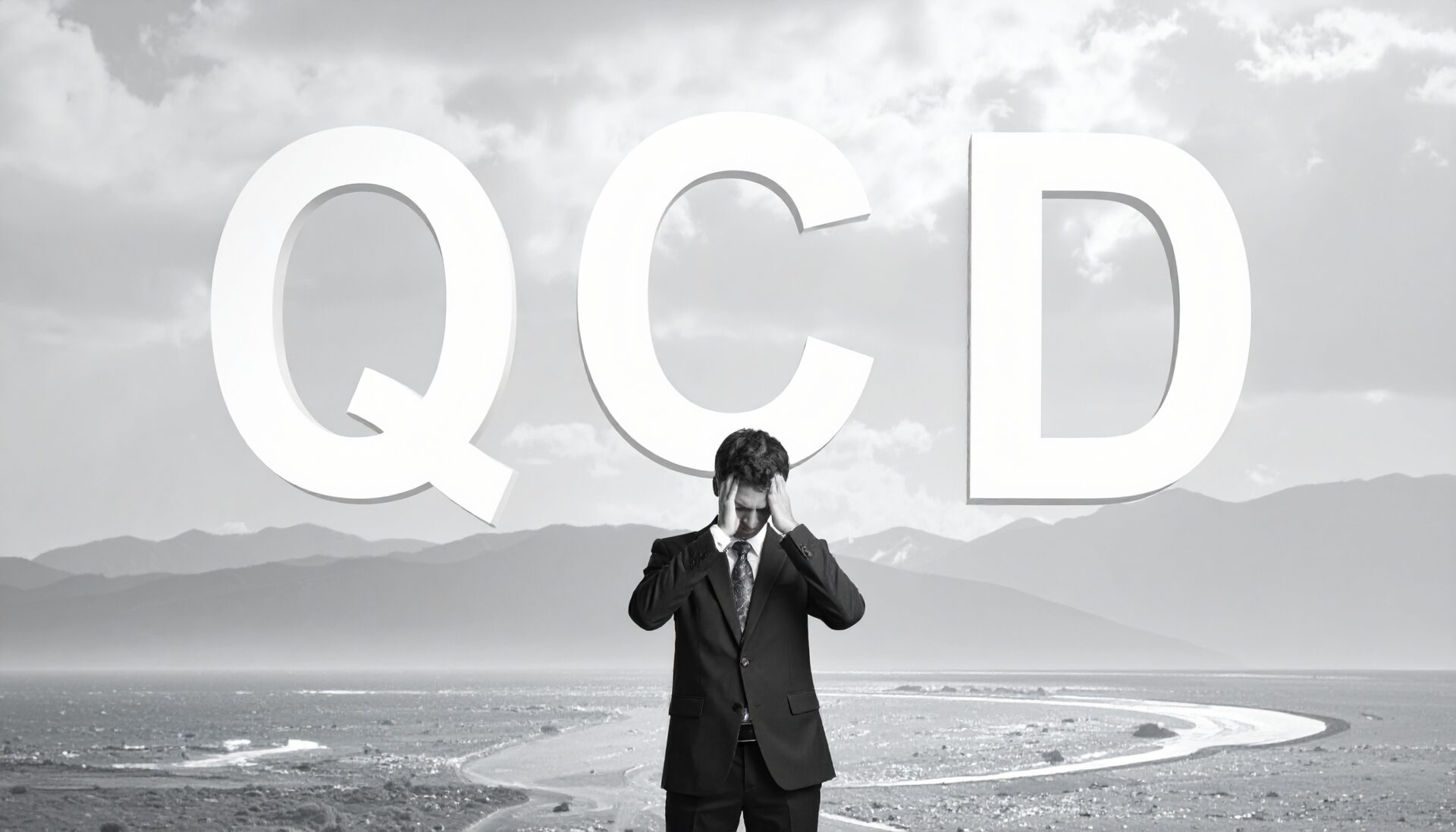
単に「速い」「安い」だけでメーカーを選んで、本当に大丈夫でしょうか。近年、一部の海外企業が日本市場から撤退した事例は、日本のものづくりに本当に必要なものは何かを問いかけています。ここでは、長期的に信頼できるパートナーを選ぶための視点を解説します。
スピードだけでは不十分?日本市場特有の品質要求
日本の製造業が世界に誇るのは、その極めて高い品質基準です。たとえ試作品であっても、機能を満たすだけでなく、外観の美しさや微細な傷一つない「完璧品質」を求める文化が根強くあります。海外では許容されるような僅かなヒケ(樹脂の収縮による凹み)やウェルドライン(樹脂が合流した跡)も、日本では問題視されることが少なくありません。
そのため、メーカーを選ぶ際には、コストや納期といった数値的なスペックだけでなく、自社が求める品質レベルを実現できる技術力があるかを見極めることが不可欠です。過去に製作したサンプルを見せてもらったり、どのような品質管理体制を敷いているのかを確認したりすることで、そのメーカーの品質に対する姿勢を判断できます。効率化を優先するあまり、こうした細かな品質要求への対応が不得意なメーカーも存在するため、事前の確認が失敗を避ける鍵となります。
逆に、量産がメインで試作対応もしているメーカーでは高品質な金型作りをする傾向にあるため、コストが高くなる可能性があります。適正品質をすり合わせることも重要です。
綿密なコミュニケーションと技術的なすり合わせの重要性
日本のものづくりの強みの一つに、設計者と製造現場が密に連携する「すり合わせ」の文化があります。特に、複雑な製品開発においては、3Dデータだけでは伝わらない設計者の意図や、懸念事項が存在するものです。オンラインで完結する手軽さは魅力的ですが、技術的な課題が発生した際に、メールやチャットだけで微妙なニュアンスを伝え、解決に導くのは容易ではありません。
本当に頼れるパートナーとは、単に注文通りに作るだけでなく、こちらの意図を汲み取り、より良い製品にするための技術的な提案をしてくれる存在です。「この部分の肉厚ではヒケやすいので、リブを追加しませんか」「この構造なら、こちらの樹脂材料の方が適しています」といった、プロの視点からのフィードバックが得られるかどうかは、プロジェクトの成否を分けます。電話での相談や、必要であれば対面での打ち合わせにも柔軟に応じてくれるかなど、双方向のコミュニケーションを重視する姿勢があるかどうかも、重要な選定基準になるでしょう。
相見積もりをした際に極端に低い見積があった場合こそ、しっかりと内容確認を行いましょう。例えば、成形機は適正なサイズを選定しているのか?外観の要求品質が高い場合には余力のある成形機サイズを選定しているのかなどは、重要なチェックポイントになります。
長期的なパートナーシップを築ける信頼性
簡易金型の製作は、一度きりの取引で終わらない可能性も視野に入れておくべきです。試作品の評価結果を受けて設計変更が生じたり、好評だったために追加生産を依頼したりするケースは頻繁に起こります。また、将来的には量産化のため、量産金型の製作へとステップアップすることもあるでしょう。
だからこそ、その場限りの取引ではなく、長期的な視点で付き合える信頼性がメーカーには求められます。継続的な関係性は、品質とコストの最適化という大きな恩恵ももたらします。例えば、初回取引では、メーカー側も顧客の品質要求レベルを完全に把握できず、安全策としてオーバースペックな(=高コストな)仕様を提案することがあります。特に日本のメーカーは顧客の意図を汲み取ることに長けていますが、その気遣いが逆に過剰品質に繋がるケースも少なくありません。
しかし、パートナーとして取引を重ね、綿密なすり合わせを行うことで、「外観部品なのでこの面の仕上げは重要だが、内部のこの部分は機能さえ満たせばいい」といった具体的な品質レベルの共通認識が生まれます。これにより、不要な工程を省いてコストを削減し、真に求める品質を適正な価格で実現できるようになるのです。
事業の継続性はもとより、製作した金型の保管やメンテナンスにどう対応してくれるのか、納品後のサポート体制は整っているか、といった点も確認しておくべきです。突然の事業撤退などで、製作した金型のデータや現物がどうなるか分からなくなるような事態は絶対に避けなければなりません。会社の設立年数や実績、そして何よりも担当者との信頼関係を通じて、開発プロジェクトを最後まで、そしてその先まで支えてくれるパートナーを見つけ出すことが、最終的な成功に繋がるのです。
まとめ
この記事では、簡易金型の費用と納期について、価格が決まる要因から信頼できるメーカーの選び方までを解説しました。簡易金型は、開発初期のコストを抑え、市場投入までの納期を大幅に短縮できる強力なソリューションです。その費用は材質や形状、求めるショット数によって変動するため、自社の目的を明確にして依頼することが重要となります。そして、単なる速さや安さだけでなく、日本の高い品質要求に応え、技術的なすり合わせができる長期的なパートナーを見つけることが、プロジェクトを真の成功に導く鍵と言えるでしょう。





